協会コラム ~だから、Medicell~
Vol.38 痛みを緩和した後が大切
痛みが起きるメカニズムが、かなり解明されてきました。ペインクリニックの分野などで、痛みが起きる末梢と中枢の仕組みが説明されています。特に、中枢のメカニズムの機能が中心。
さて、そのメカニズムにもとづいて、痛みを緩和する方法が、日の目を見るようになってきています。

痛みは、体のどこかに異常が発生しているサインだといわれています。ただし、痛みが発生している箇所に異常が起きている場合もあれば、痛みを感じる箇所に異常が発生しているのではなく、他の場所や場合によってはメンタル的な問題から、身体の痛みとして感じることもあります。
痛みが緩和したら、それらの異常が治癒したと思いがちですが、そうとばかりは言えませんね。特に、外傷の場合は特に注意が必要。
あきらかに、骨や筋肉などに損傷がある場合は、痛みが無くなったとしても、損傷が修復されたわけではないので。
即、動いたりすると、損傷部位に負荷がかかるので、損傷部位に悪影響が出るケースも。
組織の損傷がある場合は、当然ですがその組織が修復するまでに時間経過を必要とします。

痛みを緩和しておいて、組織の修復を促進するためには、まずは安静。専門的には免荷といいますが、体重の負荷、筋肉を動かす(収縮する)ことによってかかる負荷を、できるだけ減らす。
損傷した箇所に圧迫や腫れなどがあっても、循環が阻害されますので、修復が遅れます。修復するためには、栄養素が供給されることが必要です。
安静な状態で、なおかつ循環が良い状態にするには、筋膜のリリースと皮膚に刺激を発生させるのが、大変有効です。
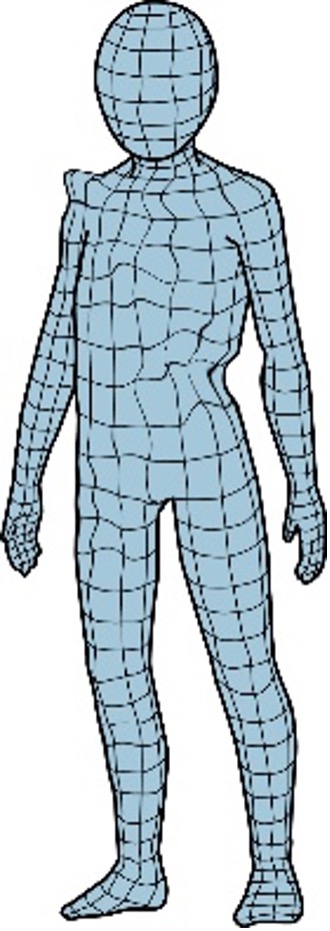
特に外傷の場合は、負荷がかからない安静状態で、循環が良い状態を保つことが、回復を促進するために重要です。
しばしば、安静を保った結果、その箇所が硬くなったり、瘢痕組織ができたりして、動かしづらくなったり、可動域が小さくなったりが起きます。
筋膜リリースと皮膚刺激で、組織の軟らかさを保ち、循環を良くすることは、外傷が起きた組織の回復に、大いに役立つでしょう。

筆者:竹内 研(一般社団法人日本メディセル療法協会理事・学術委員長)